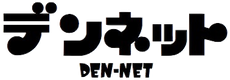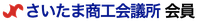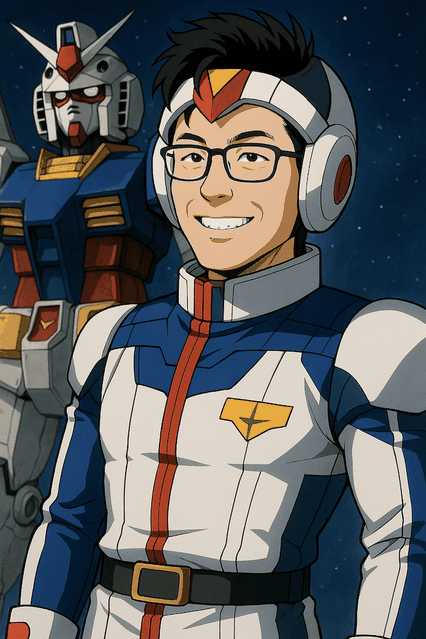
先日、このブログで
機動戦士Gundam GQuuuuuuX
を紹介しました。
機動戦士ガンダムって
私が思うに、ロボットが戦う
単なるロボットアニメだったら
ここまで長年愛されるアニメには
ならなかったのではと思いました。
この作品を
特別なものに押し上げたのは
「ニュータイプ」という要素です。
ニュータイプとは、
第六感を超えた
第七感を持つ者たちを
ニュータイプと呼びます。
危機察知能力や共感能力に優れ、
「人類の革新」とも言うべき、
人類の新しい在り方を示す
存在としてこのアニメでは
描かれています。
機動戦士ガンダムという物語は
単なるロボット戦争アニメを超えた
アニメに盛り上がった背景には
このニュータイプという哲学的概念が
設定されたからに他ならないと思いました。
これは
ある種の発明だと思います。
日本ならではの発想かも?
この機動戦士ガンダムの
そうした設定がなされたのは
日本ならではの発想なんだと思います。
おそらく外国人だったら
この発想は出なかったんじゃないかと
思うのです。
もし海外で
ニュータイプという要素が
取り入れらるとしたら、
「超能力=ヒーローになる」
「力を使って世界を変える」という
ベクトルが強くなりやすいのだと思います。
しかし、
日本人の発想はもっと繊細です。
能力を持つことで、
自己犠牲だったり、他者との共鳴だったり、
「力=苦悩」だったりする。
だからニュータイプも
「すごい能力を得た=だから幸せ」
では決してなく、
むしろ理解されない孤独や
争いを止められない葛藤を背負っています。
「悲しみを伴った進化」という発想は
日本人ならでは感性なのかも。
ニュータイプという全く新しい要素
ネットで調べたのですが、
当時の制作スタッフたちは
機動戦士ガンダムの生みの親である
富野由悠季監督から
この「ニュータイプ」という要素が
加わることについて説明されましたが
何が何だか分からなかったようです。
ロボットアニメに
エスパーや超能力者のような要素を
なぜ取り入れるのか
理解が出来なかったのだと思います。
今では第七感とかスピリチュアルとか
昔より理解されてきた時代ですが、
当時はまだここまで理解されていない
時代だったからでしょうね。
機動戦士ガンダムは
連邦軍とジオン軍との戦いを
描いた話です。
その中で、主要な登場人物たちが
ニュータイプとして覚醒し、
共鳴し合い、戦争はダメだ、
止めさせようと葛藤するわけですが。
ニュータイプっていうのは
愛と調和のエネルギーをまとった
力を持つ存在なんだなと感じました。
つまり、
敵を倒すための能力じゃなくて、
「人とつながる力」がニュータイプ。
そういう要素を盛り込んだ
このロボット戦争アニメ。
深いんだよなあ、このアニメ。
個人は大きなまとまりの中では無力?
戦争というのは一度始まったら
なかなか止めにくいものです。
なぜなら
個人ではなく、集団、
つまり組織だからです。
ガンダムに登場する
アムロとララァは
どちらもニュータイプですが、
置かれた状況(連邦軍とジオン軍)
によって戦うことになりました。
個人個人では争いたくなくても
国や組織など大きなまとまりの中に
置かれた場合、争いの場で
向かい合うことになるのだと思いました。
大きなまとまりというのは
方向性によって争いたくない個人を
巻き込むことがあるのですよね。
アムロとララァの戦闘シーンは
個人の善意や心の繋がりだけでは
どうにもできない
社会の大きな流れの恐ろしさを
ものすごく象徴的に描いています。
一人ひとりは戦いたくない、わかり合いたい。
でも、それを押し流す
システムや集団意識の中では、
個人の想いはあまりにも無力で
時に悲劇を生んでしまう。
私たちの歴史の中でも
こうした悲劇は
何度も繰り返されてきました。
ガンダムって
こうした考えさせられる
テーマも盛り込まれているから
長く愛されているのでしょうね。
私が思うに富野監督は
希望としてニュータイプを
つくったのだと思います。
戦争そのものが
なくなるかもしれないという
想いを込めて。
そんなわけで今日は
機動戦士ガンダムの
ニュータイプについて
私なりに考えたことを書いてみました。
読んでいただきありがとうございました。